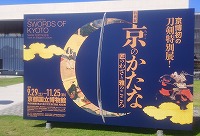
京のかたな
匠のわざと雅のこころ
宗近や吉光、国重、あの名刀が登場
・企画展会期:2018年9月29日(土)〜2018年11月25日(日)
・会場:京都国立博物館

内覧会で一足先に見てきた。3階建の新館の展示スペースが見事に刀づくしで驚いた。
刀の見方は美術館に通い続けている今でも分からない。単眼鏡で地の部分を見ていると確かにそれぞれ違うし、特徴があるというのも分かるのだが、これだけの数の刀があっても、これが特にいい!というものを見つけられない。
ただ、刀というジャンルで見れば、金銀とは違う美しさを感じるし、その刀の持つ歴史と合わさって、浪漫を感じもする。微かな刀の特徴や模様をとらえて名前を付けるのも、有名な持ち主の名前を号としているものも、人がそれだけ刀に対して強い執着を持っていたからなのだろう。
そんな中で、唯一これはなんぞ?と思ったのがはっきり名前を覚えていないのだが、五章の長谷部の刀。刃文や地の部分が妙に荒々しくて面白かった。
内覧会は時間があまりなくて、すべてをじっくり見ることができなかった。時間がとれたらもう一度行って、特に後半、じっくりと見たい。細かなところは図録で見るとして、もう少し刀そのもの、全体の雰囲気を感じたい。
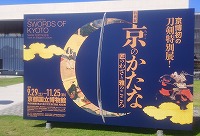
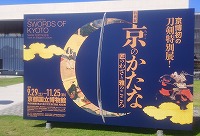
 内覧会で一足先に見てきた。3階建の新館の展示スペースが見事に刀づくしで驚いた。
内覧会で一足先に見てきた。3階建の新館の展示スペースが見事に刀づくしで驚いた。