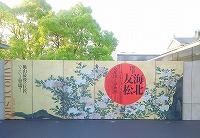
海北友松
この絵師、ただものではない!
・企画展会期:2017年4月11日(火)〜2017年5月21日(日)
・会場:京都国立博物館

初めての夜間拝観。ゴールデンウィークなので人が多いかと思ったけれど、時間が良かったのかじっくりゆっくりと見ることができた。迫力のある屏風絵や襖絵が多く、照明を落とした展示室の雰囲気も良かった。
全体をとおして思ったのは、いろんな絵を描くのだなということ。初期の、狩野派としての色が濃いざくざくとした岩肌や木々の雰囲気と、晩年の没骨で描かれるやわらかく浮かび上がるような表現はまるで違う。愛嬌のある人物の表現、勢いはあるけれどまるっとした線、繊細な動物の表現もあれば、簡略化した表現もあったり、とにかく色々な絵があって面白かった。ひとつひとつじっくりと見ていくと、どれもそれぞれの雰囲気で好き。
特筆するなら、やはり龍の絵で、顔のはっきりとした線と体や雲のもやりとした対比が面白い。顔は結構ぶさいくだなと思ったりする。墨の流れがどこまで意図的なものなのかよく分からないけれど、立て掛けて描いたということはある程度偶然だけではないのかもしれない。暗い部屋に龍が浮かび上がって見えて、とてもよかった。
「花卉図屏風」は、それまでの水墨画とはまったく違う雰囲気で、決して色数が多いわけでもないけれど、鮮やかで豪華絢爛という言葉がよく似合う。
最後に展示されていた「月下渓流図屏風」はずっと見ていたいくらいだった。とても詩的で静かな絵。何も描かれていない余白に奥行きがあって、自分がそこに立っているみたいだ。月の音が聞こえてきそうなくらいしんとした絵だと思った。
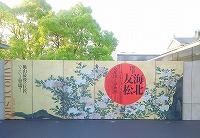
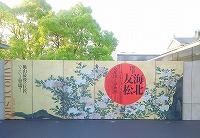
 初めての夜間拝観。ゴールデンウィークなので人が多いかと思ったけれど、時間が良かったのかじっくりゆっくりと見ることができた。迫力のある屏風絵や襖絵が多く、照明を落とした展示室の雰囲気も良かった。
初めての夜間拝観。ゴールデンウィークなので人が多いかと思ったけれど、時間が良かったのかじっくりゆっくりと見ることができた。迫力のある屏風絵や襖絵が多く、照明を落とした展示室の雰囲気も良かった。